\当サイトおすすめNo.1サイト/

サーキュラーエコノミーへの積極的な取り組みは、将来的な事業機会の獲得においても重要です。この流れに乗り遅れることは、国際社会における日本のプレゼンス低下を招く可能性も否定できません。
本記事では、なぜ日本がサーキュラーエコノミーで遅れているのかという構造的な課題を明らかにしながら、企業が今後取るべき対応策をデータ的根拠をなるべく提示しながら解説します。

サーキュラーエコノミーへの移行は、単なる環境対策に留まらず、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な戦略です。ここでは、日本企業がサーキュラーエコノミーに取り組むべき理由を解説します。
参考:成長志向の資源循環経済システム「サーキュラーエコノミー」(前編)どんな課題を解決するの?|経済産業省 資源エネルギー庁
サーキュラーエコノミーの実装は、欧州を中心に加速しており、EUでは「循環型経済行動計画」のもと、製品設計・消費・廃棄物管理・再資源化までを一気通貫で捉えた政策展開が進んでいます。
そのような背景から欧州では企業に対しても、拡大生産者責任(EPR)の強化やグリーン製品への優遇措置などが整備され、経済活動と環境保全の両立を前提とした制度設計が進行しています。
一方、日本では依然としてリサイクル・リユースなど、いわゆる3Rの枠組みにとどまった取り組みが中心です。
このような国際的な遅れは、単なる環境分野の話にとどまりません。
持続可能性を重視する機関投資家やグローバルバイヤーからの評価にも影響を及ぼし、サプライチェーンにおける取引継続や投資判断の基準として見過ごせない要素となりつつあります。「循環設計に非対応な企業=リスク要因」として扱われるリスクも、現実味を帯びてきました。
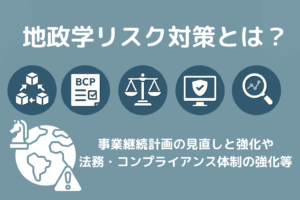
参考:資源効率・循環経済に係わる世界の動向|経済産業省
参考:【提言】エネルギー政策と資源循環政策の一体的推進 カーボンニュートラル資源立国の実現に向けて|三菱総合研究所
参考:容器リサイクル法とは|環境省
参考:家電リサイクル法のそれぞれの役割|経済産業省
地球規模での資源制約が深刻化するなか、企業は化石燃料や金属資源などの原材料調達リスクと向き合わざるを得なくなっています。
金、銀、銅、鉛、錫などは、2050年までの累積需要が埋蔵量の2倍になると予測されており、さらに供給が特定国に依存している金属資源においては地政学リスクに付随して供給途絶リスクが指摘されています。
こうした状況下において、サーキュラーエコノミーは環境対応にとどまらず、経営戦略そのものとして注目されています。使用済み製品や副産物の再利用、設計段階での長寿命化、再生素材の活用などにより、資源投入量とコストを抑えつつ、サプライチェーンの安定性も確保できます。
今後、サーキュラーエコノミーシステムの採用有無は、単なる環境対応の有無ではなく、競争力を左右する分水嶺となるでしょう。限られた資源をいかに有効に活用できるかが、持続可能な成長を遂げる企業と、変化に取り残される企業を分ける決定的な要因になりつつあります。
参考:成長志向型の資源自律経済戦略の今後のアクションについて
参考:資源循環経済政策の現状と課題について|経済産業省
【事例】ブリヂストンにおけるサーキュラーエコノミーの取り組み|ブリヂストン
ブリヂストンは、サーキュラーエコノミーの実現に向け、資源の有効活用と環境負荷低減に注力しています。特に、リトレッドタイヤ事業を核としており、摩耗したトラック・バス用タイヤの台(カーカス)を再利用し、新しいトレッドゴムを貼り付けることで製品寿命を延ばしています。これにより、タイヤの製造に必要な石油、天然ゴム、炭素といった新規資源の使用量を大幅に削減しています。
この事業は、資源調達リスクを低減するとともに、顧客にとってもコスト削減につながるメリットを提供しています。また、原材料の持続可能な調達にも取り組み、リサイクルや再生可能資源の活用を推進することで、事業全体のレジリエンスを高め、競争力の強化を図っています。
参考:環境長期目標(2050年以降):100%サステナブルマテリアル化|ブリヂストン
いま、サーキュラーエコノミーの分野で先行している企業は、業界における規範形成者の地位を築きつつあります。サステナブル経営の実践者として、投資家・消費者・行政など多様なステークホルダーからの高い信頼と評価を獲得しています。
重要なのは、先に動くこと自体が価値を生む視点です。制度が追いつく頃にはすでに差がついており、追従する企業との差は簡単には埋まりません。
創り出す側に回ることが可能な現在に行動を起こす企業こそが、サーキュラーエコノミー時代の中心に立ち、持続可能な社会と企業価値の両立を実現する主役となるのです。サーキュラーエコノミーシステムの構築に関して、以下の記事で詳しく解説しています。

【事例】IKEAにおけるサーキュラーエコノミーの取り組み|IKEA
イケアは、従来の「大量生産・大量消費」モデルからの脱却を目指し、サーキュラーエコノミーへの転換を積極的に進めています。その取り組みは、製品の長寿命化、新たなビジネスモデルの導入、そして顧客との関係強化に焦点を当てています。
家具のレンタル・サブスクリプション: 顧客が一定期間だけ家具を利用し、不要になれば返却するサービスを試験的に導入しています。これにより、製品を長く使い続け、廃棄物を減らすことを目指しています。
家具の買い取り・再販: 使用済み家具を買い取り、メンテナンス後に再販することで、製品の寿命を延ばし、資源の循環を促進しています。
これらの取り組みは、単に環境に配慮するだけでなく、製品をサービスとして提供することで、継続的な収益源を確保し、顧客との長期的な関係を築く新たなビジネスモデルを構築するものです。
参考:サーキュラービジネスの実現|IKEA
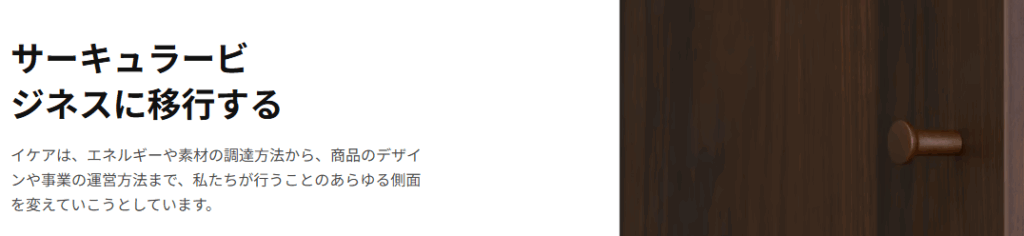

欧州連合(EU)や北欧諸国はもちろん、中国や韓国といったアジア諸国も、政府主導で急速に再生可能エネルギーの導入や資源循環システムの構築を進めており、そのスピード感は目覚ましいものがあり、日本国内においては、依然として大きな差が存在しているのが現状です。
ここでは、サーキュラーエコノミーにおける日本の遅れの実態について解説します。
EUや北欧諸国では、サーキュラーエコノミーへの移行が国家戦略レベルで明確に位置づけられ、法制度・産業政策・消費者行動のすべてを巻き込んだ包括的アプローチが進行しています。以下の動画(5:13~)では、東京大学大学院の教授によるEUのサーキュラーエコノミーの動向に関する解説をご確認いただけます。
EUで2020年に発表された「新サーキュラーエコノミー行動計画(CEAP)」のもと、以下のような具体的施策が実行されています。
| 取り組み内容 | 概要 |
|---|---|
| 持続可能な製品を規範とすることに関するコミュニケーション | EUのサーキュラーエコノミー関連政策全体を総括し、持続可能な製品を標準とするための包括的な方向性を提示。 |
| 持続可能な製品のためのエコデザイン規則案 | エコデザイン要件の対象品目を拡大し、循環性の確保、デジタル製品パスポートの導入、廃棄禁止などを規定。 |
| 2022~2024年エコデザイン・エネルギーラベル作業計画 | 循環性を含む製品のエコデザイン要件を実施・強化・策定するための具体的な作業計画を策定。 |
| 持続可能な循環型繊維製品戦略 | 繊維製品の持続可能性向上を目的に、ファストファッション対策、マイクロプラスチック削減、繊維廃棄物輸出規制、産業の社会的課題への対応を推進。 |
| 建設資材規則改正案 | 建設資材の標準化を促進し、循環性に関する要件を強化。 |
| グリーンへの移行に向けた消費者のエンパワーメントのための消費者ルールの改正 | 耐久性・修理可能性の情報提供を義務化し、早期陳腐化やグリーンウォッシュ(実質のない環境訴求)を禁止。 |
こうした政策は、経済成長・雇用創出・産業競争力の強化を一体で進める戦略として実行されています。結果、EUでは企業・自治体・消費者のすべてが連携し、資源効率と環境負荷低減を同時に達成する体制が構築されつつあります。
参考:2024年版 概要スライド EU循環型経済関連法の最新概要
近年、中国や韓国をはじめとするアジア諸国では、サーキュラーエコノミーが国家戦略の中核に据えられ、法整備・制度導入・産業構造の転換が急速に進んでいます。特に注目すべきは、政府主導による迅速かつ強力な実行力です。
中国では2021年7月に策定された循環経済発展計画により、製造業に対して再生資源の活用や副産物の再利用が義務付けられ、経済成長と資源効率の両立を国策として推進しています。以下の報道動画では、不法投棄が相次いでいた過去とごみの輸入を禁止してからの中国について紹介されています。
一方、日本では、不法投棄の新規判明件数はピーク時の平成10年代前半に比べれば大幅に減少したものの、令和5年度だけでも年間100件・総量4.2万トンの不法投棄が新たに発覚し、そのうち5,000トン以上の大規模事案が2件(計2.6万トン)を占めました。
また、不適正処理も年間121件・総量5.0万トンが発覚しており、不法投棄とあわせて撲滅には至っていません。令和5年度末時点では、残存事案が2,876件、残存量は1,011.2万トンにのぼります。
各自治体では支障除去や環境モニタリング、立入検査などを進めていますが、完全解決にはまだ時間を要する状況です。
出典:https://www.env.go.jp/press/press_04046.html
韓国も資源循環に関する枠組み法に準ずるロードマップを策定し、資源有効利用システムの構築やグリーン消費の推進など、多面的な取り組みを加速させています。
特に食品ロス削減とリサイクルが活発化しており、2007年時点で生ごみリサイクル率は90%を記録しています。
一方、日本はごみの種類によって進捗に大きな差があり、生ごみは特にリサイクルが進んでいない品目の一つです。平成24年度時点での全体リサイクル率は20.4%であり、平成元年度(4.5%)と比較して4倍以上に向上しています。
しかし、多くの自治体では、生ごみが可燃ごみとして焼却処理されており、資源循環の仕組みづくりが十分に整っていません。
出典:https://www.env.go.jp/press/press_04046.html
日本ではこれまで、資源循環政策といえばリサイクルの推進が中心でした。
確かに、分別回収や再資源化の仕組みは一定の成果を上げているものの、より上流の工程であるリデュース(削減)やリユース(再利用)への実装が極めて限定的であり、製品の設計・使用・再流通といった段階での循環設計が社会全体に浸透していないのが実情です。
こうした状況は、廃棄物の統計データにも表れています。環境省の調査によれば、日本のごみ総排出量は2000年代前半をピークに減少傾向にあり、一人一日当たりの排出量も約1,400gから900g台へと低下しています。これは、分別回収の普及や処理効率の向上など、従来型の資源循環政策が一定の成果を上げてきた証拠です。
しかし、排出量が減った一方で、依然として多くの廃棄物が焼却や埋立に回されており、その出口となる最終処分場の残余容量は長期的に減少を続けています。
全国平均の残余年数は20年前後を推移しており、将来的な容量逼迫は避けられません。このまま現状の処理構造が続けば、埋立依存による環境負荷やコスト増大が顕在化する恐れがあります。
つまり、日本はごみの量的削減には一定の成果を上げつつも、資源を製品ライフサイクル全体で循環させるというサーキュラーエコノミーの本質的な実装には至っておらず、出口制約の克服と上流工程での循環設計が喫緊の課題となっています。


日本がサーキュラーエコノミーの国際的な潮流に対して後れを取っている背景には、静脈産業に過度に依存する産業構造や「リサイクルさえ進めばよい」という発想の限界に象徴されます。ここでは、そのような構造的課題を順に解説します。

日本ではこれまで、資源循環の多くが廃棄後の段階に着目したリサイクル中心の静脈産業によって支えられてきました。
確立された分別収集や再資源化インフラは一定の成果を上げており、特にペットボトルのリサイクル率は2023年度で85%と、欧州(42.7%)や米国(19.6%)を大きく上回り、世界最高水準を維持しています。
しかし、この高い数値はあくまで廃棄された後に素材として再利用するプロセスでの成果であり、リニアエコノミーの延長線上にある対症療法的な対応にすぎません。
製品を廃棄してから素材に戻す過程では、多くのエネルギー・労力・コストが失われ、資源効率という観点でも限界があります。
真のサーキュラーエコノミー実装には、このリサイクル偏重から脱却し、動脈産業(設計・製造・流通)の段階で資源循環を組み込む発想への転換が不可欠です。たとえば、商品設計の段階で再利用を前提としたモジュール化や原材料にリサイクル材を利用するなどが挙げられます。
静脈依存型から経済全体の循環構造へと設計を変えることこそ、持続可能な競争力の源泉となります。
参考:今注目される「静脈産業」とは|オリックス
参考:リニアエコノミー(直線型経済)とは|新電力ネット
【事例】サントリーのサーキュラーエコノミー
サントリーは、ペットボトルの「ボトルtoボトル」リサイクルを推進しています。これは、使用済みのペットボトルを洗浄・粉砕して原料に戻し、再びペットボトルとして製品化する取り組みです。これは、単にプラスチックを別の用途にリサイクルするのではなく、同じ用途で資源を何度も循環させる「水平リサイクル」であり、資源効率の向上に貢献しています。
参考:資源をつなげる未来へ|サントリー
たとえば欧州諸国では、製品設計の段階でエコデザイン規制やリサイクル材の用義務、環境配慮型製品に対する税制優遇措置など、法的・経済的両面から企業の循環型ビジネスモデルへの移行を支援する仕組みが整っています。
これらは衣料品を中心にその仕組みを確立しており、実際に「過剰生産・過剰廃棄を助長させるファストファッションは持続的ではない」と2022年3月の「持続可能な循環型繊維戦略」でEUが公に声明を出しています。
日本では2020年の衣類の国内新規供給量は計81.9万トンに対し、その約9割にあたる計78.7万トンが事業所や家庭から廃棄されています。
こういった直接的な数値以外にも、国内に供給される衣類から排出されるCO2(原材料調達から廃棄まで)は95百万トンと推計されており、このCO2排出量は世界のファッション産業において4.5%を占めるなど、日本の衣料品業界および公的機関を巻き込んだ仕組み作りが遅れていることが浮き彫りとなっています。
出典:https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/textile_nw/pdf/010_03_00.pdf
【事例】WORLDのサーキュラーエコノミー|WORLD
ワールド(WORLD)社は「ウール再生」でGHG(温室効果ガス)排出量を約33.7%削減、「再生ポリエステル×オーガニックコットン」で23.4%削減の製造モデルを推進しています。原料調達~製造~販売で供給ヤーと連携した共同開発も進んでいます。
参考:資源循環経済の成長に向けたアパレル産業の取り組み事例|日本アパレル・ファッション産業協会
日本企業の多くは、部品調達から製造、販売、アフターサービスに至るまでを自社または系列企業で完結する垂直統合型のビジネスモデルを長年にわたり採用してきました。
この構造は品質管理やコスト最適化の面で一定の強みを持つ一方で、サーキュラーエコノミーの前提となる企業横断的な資源循環には適合しづらいという課題があります。
サーキュラーエコノミーの実現には、素材メーカー・製造業者・流通業・回収業者・再生事業者・消費者といった多様なプレイヤーが、業種や業態を超えてライフサイクル全体を通じた協調関係を築くことが不可欠です。
ところが日本では、他社との情報共有や再設計を前提とした連携が進まず、水平連携の基盤が非常に脆弱です。
この背景には、単に構造的な問題だけでなく、売って終わりという従来的発想に根ざした企業文化も関係しています。製品寿命の延長や修理・再流通といった取り組みは、「新製品販売による収益確保」という従来のモデルと利益構造が異なるため、経営判断における優先順位が低くなりがちです。
さらに、日本企業には変化を慎重に捉える保守的な傾向が強く、制度や市場の後押しがない限り、新しいビジネスモデルへの転換に対して積極的に舵を切る企業はごく一部にとどまっています。このような文化的な要因も、サーキュラーエコノミーの国内展開を鈍化させる温床となっています。
【事例】伊藤忠商事などの「RENUプロジェクト」
伊藤忠商事は、繊維製品のリサイクルにおける水平連携を推進する代表的な事例です。
同社は、自社だけではなく、国内外の多様な企業と連携し、使用済み繊維製品から再生原料を生産し、それを再びアパレル製品に利用する「RENUプロジェクト」を主導しています。
・サプライチェーンの構築: アパレルブランド、リサイクル技術を持つ企業、素材メーカーなど、異なるプレイヤーが連携して、繊維製品の循環システムを構築。
・ビジネスモデルの変革: 従来の商社機能に加えて、リサイクル原料の安定供給を保証する新しい役割を担い、持続可能なサプライチェーンのハブとなっています。
参考:ポリエステルのケミカルリサイクル技術に関するライセンスに向けた3社共同協議書の締結について
参考:RENU Project
日本では3R(リデュース・リユース・リサイクル)の概念が広く知られ、特にリサイクルに関しては一定の定着を見せています。しかし、廃棄後のアプローチがメインの3Rだけでは本質的な循環経済への移行が困難なのが現状です。
たとえば下記のリユースショップで購入しなかった理由をみると、リユースショップの店舗数に言及する意見や、購入価格と保証体制などに関する不安が高い割合を占めており、これらは現状の体制に改善の余地があることを示しています。
しかしこういった俯瞰的視点を前提とする改革となれば、業界関係者だけでの改善は困難です。リユース品に関する法整備を含め、公的機関をも巻き込んだ体制整備が求められます。

ここまでで解説したように、法整備などの取り組みは公的機関に任せるほかありません。
しかし企業も消費活動に深く関わるため、新しい経済活動に向けた対応策を行う必要があります。
企業がまず取り組むべきは、「製品は売って終わり」という線形経済の概念を捨てることです。製品を繰り返し価値を生み出す資源として再定義する発想が必要です。たとえば以下のような取り組みが、サーキュラーエコノミーのビジネスモデルとして有効です。
| 耐久性向上 | 壊れにくい設計、長期使用を前提とした開発 |
|---|---|
| 修理・メンテナンスサービスの提供 | パーツ販売や修理受付の仕組み化 |
| サブスクリプションモデルの導入 | 所有から利用への転換 |
| シェアリングエコノミーへの対応 | 一製品を複数人で使用するモデル |
| 使用済み製品の回収と再資源化 | クローズドループの構築 |
これらの施策は、単に資源効率を高めるだけでなく、顧客との長期的な接点の創出や継続的な収益源の確保といったビジネス上のメリットももたらし、サービスとしての提供は、モノの価値を維持・向上させながら関係性を深化させる手段として注目されています。
企業が製品のその後にまで責任を持ち、価値の循環を設計することこそが、次世代のスタンダードとなるでしょう。
【事例】パタゴニアのWorn Wear|パタゴニア
パタゴニアは、製品の耐久性向上と修理・再利用を核としたビジネスモデルを確立しています。同社は「最高の製品を作り、環境に与える不必要な悪影響を最小限に抑える」というミッションのもと、製品を長く使い続けることを推奨しています。
・Worn Wear(ウォーン・ウェア): 顧客から不要になったパタゴニア製品を買い取り、修理して再販するプログラム。これは、製品を「売って終わり」ではなく、繰り返し価値を生み出す資源として扱う象徴的な取り組みです。
・生涯修理保証: 製品が壊れた際に修理サービスを提供し、顧客が長く製品を使えるようにサポートしています。
参考:Worn Wear|パタゴニア
サーキュラーエコノミーの実現には商品ライフサイクル全体に対するアプローチを講じる必要があるため、自社単独の努力では限界があり、複数の企業・業種をまたぐ共創型の連携が前提となります。たとえば、以下のような連携が重要です。
こうした連携を通じて、製品のライフサイクル全体を見渡した資源循環スキームの最適化が可能になります。とくに注目すべきは、共同投資や技術共有によって、単独では実現が難しいコスト削減やスケールメリットが得られる点です。
また、このようなオープンイノベーション型の取引設計は、新しいサービス・商流の創出や特定企業への依存度を低下させたリスク分散など、副次的な効果も期待できます。
今後は、自社のバリューチェーンの中に「誰と循環を設計するか」という視点を組み込むことが不可欠です。循環型経済における競争優位は、単なる技術力ではなく、連携力と共創力によって築かれていくでしょう。
参考:取組事例|J4CE(環境省、経済産業省、経団連)
参考:サーキュラーエコノミー型ビジネスモデルへの転換に向けた重要な視点|日本経済研究所
サーキュラーエコノミーの推進において、とくに、製品の回収や再利用に参加してもらう意識向上を目的とする仕組みづくりは、企業と顧客の関係を再構築し、持続可能なブランド価値を高める上で重要な要素です。
そこで有効なのが、リターン型マーケティングの導入です。これは、製品を使用した後も消費者とつながり続け、回収・再資源化・再販売などの循環プロセスに巻き込むマーケティング手法です。たとえば、以下のような取り組みが注目されています。
消費者庁によるエシカル消費の実践度に関する調査によると令和6年度時点で36.1%であり、前年度の27.4%よりも増加しています。さらに10代20代の若年層で高い実践度を示しており、これは今後の商品設計においてより環境に対する配慮が重要視されることが予測されます。
エシカル消費が今後ますます向上することを想定すると、循環型を前提とした商品が追い風になる一方で、従来型の廃棄を前提とした商品は消費者に避けられることも懸念されます。
近未来の需要に応えるためには、早期にサーキュラーエコノミーを前提とする商品設計が求められます。
【事例】JEPLANのサーキュラーエコノミー戦略|JEPLAN
JEPLAN(ジェプラン、旧:日本環境設計)は、「あらゆるものを循環させる」をビジョンに掲げ、独自のケミカルリサイクル技術「BRING Technology™」を事業の中核に据えています。この技術は、繊維製品やプラスチックを分子レベルで分解し、新品と同等の原料に再生するもので、従来の物理的なリサイクルでは困難だった高度な資源循環を可能にします。
この技術を基盤に、同社はアパレルブランドや自治体と連携し、消費者参加型プラットフォーム「BRING™」を運営。不要な衣類やペットボトルを回収し、「服から服へ」「ボトルからボトルへ」といった水平リサイクルを実現しています。JEPLANの取り組みは、企業や消費者を巻き込む形で、サーキュラーエコノミーの構築に取り組んでいます。
参考:BRING公式サイト
参考:事業領域 アパレル事業|JEPLAN
たとえば、IoTセンサーを製品に組み込むことで、使用状況や稼働時間のリアルタイム把握や劣化兆候の検知による予兆保全・最適タイミングでの修理提案が可能となります。
AI分野では、使用済み製品に含まれる素材の自動識別・分類によるリサイクル効率の向上や生産・流通・回収における最適ルートの計算や予測分析が期待できます。
こうしたデジタル技術とサーキュラー設計の融合により、定量的に資源の動きが可視化され、資源ロスや余剰在庫、不要な廃棄の削減が実現し、データに基づく設計・運用のサイクルは、企業全体のサステナビリティ経営の高度化にも直結します。
さらにこうした取り組みは、新たなサービス価値の創出にもつながります。たとえば、利用状況に応じたカスタムサポートプランや、環境貢献度を見える化した顧客向けフィードバックなど、デジタルならではの付加価値提供も可能となります。

参考:令和4年度 流通・物流の効率化・付加価値創出に係る基盤構築事業(サプライチェーンにおけるデジタル技術活用実態等調査)|みずほリサーチ&テクノロジーズ
日本のサーキュラーエコノミーは、リサイクル中心の静脈産業依存や制度の不備により、欧州やアジア諸国に比べ導入が遅れています。
循環資源活用が経済競争力に直結することが予測される以上、日本の競争力を維持するためには、法整備が急がれるとともに、企業においても上流から下流まで一体的な循環システムを構築する必要があります。
早稲田大学法学部卒業後、金融機関での法人営業を経て、中小企業向け専門紙の編集記者として神奈川県内の企業・大学・研究機関を取材。
2013年から2020年にかけては、企業のサステナビリティレポートの企画・編集・ライティングを担当。2025年4月よりフリーランスとして独立。
企業活動と社会課題の接点に関する実務経験が豊富で、サステナビリティ分野での実践的な視点に基づく発信を強みとしている。